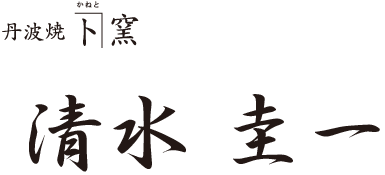
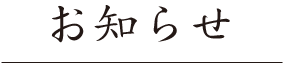
2023.03.05清水圭一 陶展 Reborn
2021.06.12個展開催中
2021.05.18個展 「玄と白」
2021.05.12お休み 告知
2021.04.28かねと窯 GWの営業について
≫ もっと見る
丹波焼は、瀬戸、常滑(とこなめ)、信楽(しがらき)、備前、越前と並んで日本六古窯の一つに数えられるほど有名な焼き物です。もともとは大きな壺やすり鉢などを作っていましたが、その後、現在のような茶碗などの食器も作るようになりました。
窯による焼成は1300度に達する高温で約60時間続きますが、その際に窯の燃料である薪の灰が器に降りかかります。そして、その灰が釉薬と融け合って変化し、一品ずつ異なるさまざまな模様や色が生まれます。これが「灰被り(はいかぶり)」と呼ばれる丹波焼の大きな特徴です。また、「丹波の七化け」と称されるほど釉薬の種類や装飾の技法に変化が多いことも丹波焼の特徴の一つです。
今では、丹波立杭(たちくい)焼や丹波焼など、さまざまに呼ばれていた名称を丹波焼と統一し、丹波地方で約60もの窯元が作品を作り続けています。